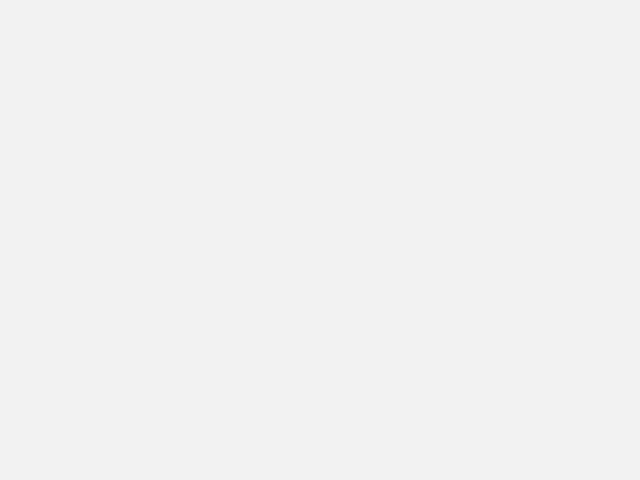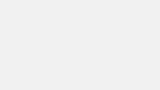また刑の軽さを告げるウェブ記事に女が蹂躙される広告
頬をぶつ 同じ手でたまに頬を撫でる それでやってきたんだろ、わかるよ
私をだめなやつだと思わせるやつと闘ってほしい 倒れないでほしい
(小松岬 連作『営為』より)
ローズ・グラス監督『愛はステロイド』(2024)を観た。
終盤、暴力で家族を支配する父(エド・ハリス)に痛めつけられるルー(クリステン・スチュワート)を、ルーの恋人であるジャッキー(ケイティ・オブライエン)が作中のリアリティラインを大幅に揺るがすほどの巨人になって助け出したシーンで、私は思わず大声で叫びたくなった。
なんて叫ぶか? わからない。でもたとえばもし指笛が吹けたなら、空高らかに吹き鳴らしたいような気分だった。もちろん叫ぶにせよ指笛にせよ、映画館でなく自宅にいたらの話だが。
背中がじんわり汗ばむような高揚感にしばし浸ったあと、今度は涙がこぼれそうになった。
私には、昔よくしていた妄想がある。つらいとき、苦しいとき、怖いとき、恥ずかしいとき、ざっくり言えば「ここにいたくない」とか「消えてしまいたい」と感じるときに、自分の体を極小サイズに変えてピンチを逃れるというものだ。シルバニアファミリーの人形よりも小さい。芝山努監督『ドラえもん のび太とブリキの迷宮』(1993)で、ナポギストラー一世の口のなかにディスクごと飛び込んでいくミニドラくらいのサイズを思い描いてほしい。
体が小さくなれば誰にも見つからない。小さくなって、ティッシュボックスの影や本棚のすきまや写真立てのうしろに隠れて、時が過ぎるのをひっそりと待ちたい……。そんな妄想をしょっちゅうしていた。
『愛はステロイド』のジャッキーはボディビルダーだ。彼女の筋肉はステロイドの過剰投与により増強されている。極端な巨人化はそれを一因とすると同時に、女性への暴力や抑圧に対するほとばしる怒りを可視化するメタモルフォーゼである。
ジャッキーを見て気づいた。私は、ほんとうは、小さくなんてなりたくなかった。
小さくなって息をひそめて危機をやり過ごす、なんて消極的なことはせず、ジャッキーみたいに巨人になりたかった。遠く離れた場所からもその姿が見えるような、世界中の誰もが目撃しておののくような、目撃されたあとは畏怖の対象として各地の民話になって百年も二百年も語り継がれるような、ばかでかい巨人になりたかったのだ。
目が覚める思いだった。
「女の子はお腹を冷やしちゃいけないよ。下着の上には必ずもう一枚、あたたかいパンツを重ねて履くこと。もしも男の人にレイプされそうになったとき、パンツを一枚脱がされても重ね履きしていることが相手に伝われば、それ以上脱がせるのが面倒くさくなって運良く諦めてもらえるかもしれないからね」
これは私が幼い頃、おそらく当時50代前後の女性に言われた言葉である。こうして初めて文字にしてみると、あまりのインパクトに改めて呆然としてしまう。
「女の子はお腹を冷やしちゃいけない」の部分だけは、身近な大人たちから何度も聞かされたフレーズだ。それが単に、冷えがもたらす便秘や頭痛や生理痛など一連の体調不良の緩和・解消をうながすだけではなく、「将来の妊娠に備えた健康な体づくりを若いうちから心がけましょう」というニュアンスが色濃くまとわりつく、いわゆるプレコンセプションケアの一環であることに、当時の私はうっすら気づきつつも「そういうものなのかなぁ」と受け止めていた。
だが、「パンツを重ね履きしてレイプを諦めてもらいましょう」はさすがに聞いたことがない。
彼女は笑っていた。うんと年下の私に、きつめのジョークを言ったつもりだったのか。もしくは自身のなにかしらの経験を踏まえて、軽い口調に本気の教訓を込めたのか。
私は、つられてへらへら笑ったのか、それとも黙ったのか、覚えていない。ひどく居心地が悪かったことだけを昨日のことのように覚えている。
しかし振り返ってみれば、「パンツを重ね履きしてレイプを諦めてもらいましょう」の教えと、「小さくなってやり過ごしたい」の妄想は、自分を害するものへの対処の方向性において、根本的にはそうかけ離れていないのではないか。
藤田和日郎による短編・中編シリーズ『黒博物館』の一作『ゴーストアンドレディ』(2014~2015)で、主人公のフローレンス・ナイチンゲール(=フロー)は、病棟の見回りに向かう夜、兵士たちに襲撃される。医療改革を推し進めるフローを目の敵にする軍医長官から彼女を亡き者にせよと指示された彼らは、彼女をレイプしてから殺そうと目論むのだ。
だが兵士たちの計画は破綻する。格闘技の心得やケンカの経験などないであろうフローが、彼らの拘束を逃れ、獣のように吠えて威嚇しながら反撃するのだ。なぜそんなことが出来たのかというと、フローに取り憑いているゴースト〈灰色の服の男〉ことグレイがあらかじめ彼女に戦い方を教え、備えていたからである。※当該シーンは、同作を原作としたミュージカル 劇団四季『ゴースト&レディ』では変更されている。
野木亜紀子によるオリジナル脚本ドラマ『フェンス』(2023)では、沖縄でカフェを経営する大嶺桜(宮本エリアナ)が沢田和行(板橋駿谷)にレイプされそうになるのを、東京から来たライターの小松綺絵(松岡茉優)がすんでのところで救出する。メッセージアプリで送られてきた位置情報を頼りに桜のもとへ駆けつけ、和行を殴打した綺絵の手に握られていたのは、近所の家から咄嗟に拝借したシーサーだった。
先に述べた『愛はステロイド』に大きな影響を与えているであろうリドリー・スコット監督『テルマ&ルイーズ』(1991)では、バーの駐車場で男性客にレイプされかけるテルマ(ジーナ・デイヴィス)を、親友のルイーズ(スーザン・サランドン)が男性客を射殺して守る。ふたりは逃亡するも警察に追い詰められ、最終的には車ごと崖から飛び降りることを選ぶ。唯一、彼女たちに同情と思いやりの心を寄せていた刑事のハル(ハーヴェイ・カイテル)は、ふたりの車を最後まで懸命に追いかけていた。
暴力が人の心と体に刻みつける傷の深さと、およそ実現不可能なやりかたも含めた祈りのような救いと、絶望と、交錯するあらゆる感情と、なにより実社会への問題提起を根気強く私に示し続けてくれたのは数多の物語だ。時代のうつろいとともに変わるもの、変わらないものを複雑に織り交ぜながら、物語は私の人生に並走する。「パンツを重ね履きしてレイプを諦めてもらいましょう」なんて悲しい“ジョーク”に取り返しのつかないほど挫けずにいられたのは、間違いなく日々観る映画やドラマや漫画のおかげである。
あの笑えない“ジョーク”の衝撃を、私は生涯忘れないだろう。けれど、発言した彼女をうらめしく思う気持ちは年々ゆるやかに変質しつつある。彼女ではなく、彼女にあの発言をさせたものに目をこらさなければならない。それこそが本丸だから。
すこし前、ある状況下において、許可していないのに他人に体を触られた。
彼の手が私の体に触れたのはほんの数秒のことだったが、当然ながら時間など一切関係なく、クソみたいな気持ちになった。
クソみたいな気持ちになりながらも、彼の手を払いのけたりその場で抗議したりすることはついにできなかった。
すばらしいフェミニズム作品を山ほど観て勇気をもらっても、パンツ重ね履き云々の教えが間違っていることを確信できても、心身を他人に支配される瞬間はなかなか無くならない。暴力をふるわれたくない、傷つけられたくないという防衛本能は、加害に屈服するかたちで顕れがちだ。自分で自分を価値のないものとして扱えば命だけはかろうじて助かる可能性が高まるから、今以上ひどい目に遭いたくないから、卑屈にさせられてしまう。
あの“ジョーク”を言った彼女も、さまざまな意味において卑屈にさせられてきたのかもしれない。そうせざるを得なかったのかもしれない。自身が身につけた卑屈さを、年若い世代に「この世の必需品」や「生きぬくための知恵」として、良かれと思って渡してしまうほどに。自分より遥かに力が弱く、若く、守られるべき人にかける適切な言葉を見つけるのは、時に自分自身を守ること以上に難しい。
でも私はもう、同じバトンを繋いではいけないと知っている。
かつては心を守ってくれた大切な妄想だが、豆粒のように小さな体になりたいとは、もう思わない。
今となっては巨人になりたいわけでもない。
巨人として力を行使して恐れられるのではなく、人間として尊重されたいのだ。
先日、知り合いの小学生の女の子と話す機会があった。カートゥーンネットワークオリジナルアニメ『スティーブン・ユニバース』(2013~2020)を薦めたところ、かなり長いシリーズものにもかかわらず、あっという間に全話観終えていた。
じゃあこれはどう? すごく格好いいよと、今度はオーディション番組『No No Girls』(2024~2025)を薦めてみたが、そちらはまったく惹かれないらしい。大人から薦められようがなんだろうが、興味がないものは無理して観ない人であることに、勝手ながら非常に安心した。
しかし、私の発言や行動が彼女に与え得る影響については、これからも慎重に考え続けなくてはならない。
私が彼女に渡せる「必需品」や「知恵」はなんだろう。とりあえず今のところは、『スティーブン・ユニバース』が彼女に良い思い出を残したことを願うばかりである。