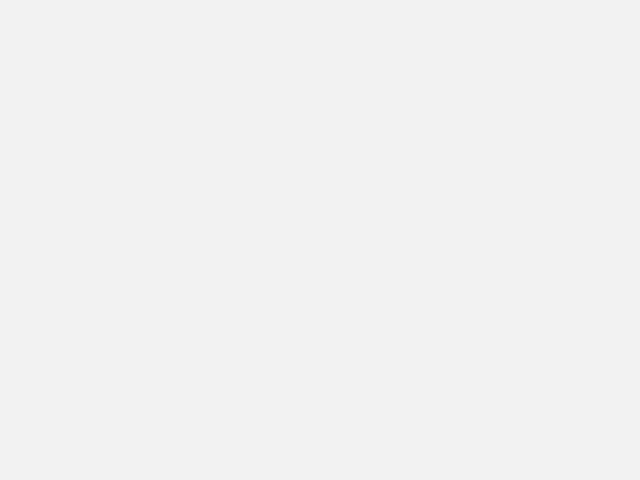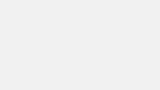星置みなみは東京で働く23歳の女性。フォロワー4人の非公開Twitterアカウントで、表立っては言えない愚痴や本音を吐き出すのがひそかな習慣だ。本命の恋人と数多の浮気相手を行き来する恵比島千歳に片思い中だが、望みは薄い。みなみの相互フォロワーで友人の栗山由仁は、不誠実な千歳に振り回されるみなみに呆れつつも心配している。
みなみはある日、池袋駅の地下道で、見知らぬ男性からわざとぶつかられて転倒してしまう。身体的な痛み以上に精神的なダメージを受けるみなみ。呆然としていると、巨大な魚を胸の前で抱えるような奇妙なポーズの男性が「大丈夫ですか?」と声をかけてきて……

瀧波ユカリ著『わたしたちは無痛恋愛がしたい 〜鍵垢女子と星屑男子とフェミおじさん〜』(2022年、講談社)は、性差別の問題を「男性vs女性」ではなく、「女の敵は女」論にも与せず、あくまでも社会構造で語りつくす真摯なフェミニズムコミックである。複数のキャラクターの視点を交錯させながら、性差別によるさまざまな苦しみや葛藤を多面的に掘り下げてゆくのが見どころだ。
トピックが多岐にわたる本作において、私がもっとも心惹かれるのはみなみと由仁の関係だ。生まれ育った環境、性格、恋愛のスタンス、フェミニズムとの距離感などが異なるみなみと由仁が、10年の空白を経ておそるおそる交流を再開する展開がとても気になる。だって、これは女友達同士の「タフラブ」の実践ではないかと思うからだ。
「タフラブ」とはなにか。信田さよ子著『タフラブ 絆を手放す生き方』(2022年、dZERO)より以下を引用する。

「タフラブ」(tough love)は、日本語では「手放す愛」「見守る愛」などと訳されている。
このことばは最初、「アラノン」(Al-Anon)という、アルコール依存の問題を持つ人の家族や友人の自助グループ(アメリカでアルコール依存症の夫を持つ妻たちが中心になってつくられた)で使われたとされている。その背景には、アルコール依存症者の妻たちの長い苦闘の歴史がある。(p18)
アラノンには多くのアルコール依存症者の妻たちの経験を通した知恵が結実している。
たとえば「これ以上飲むと死ぬよ」と酒を取り上げたり、「このまま飲み続けるんだったら別れる」と脅したりすることは、結果的に夫がもっと酒を飲むことにつながる。むしろ、「飲むか飲まないかは、あなたの問題です」と距離をとった言い方をして、飲んでいる夫を家に残し、自分はアラノンのミーティングに出ることを続ける。このような対応が積み重なった結果、酒をやめる夫があらわれた。
(中略)
密着し、尽くすことで夫を救うことはできなかった。それよりも、勇気をもって手を放すことが、結果的にアルコール依存症から夫たちを救った。それこそが、愛なのではないだろうか。やさしく不安に満ちた壊れそうな愛ではなく、勇気に満ちた愛。そこから生まれたことばが、「タフラブ」なのである。
家族のために尽くすことは、日本では「よいこと」とされている。とくに女性にとっては夫や子に尽くすことは「これぞ女の鑑」と言われ、評価される。二〇二二年になってもそれは変わっていない。
はたしてそうなのかと疑問を投げかけ、反転させるような「タフラブ」の考え方は、まさに革命的といえるだろう。(p22-23)
「タフ」ということばには、伝統的な「ラブ」の概念をひっくり返す意味合いが含まれている。それまでのラブの概念はアタッチメント(愛着)を基本としていたが、それをひっくり返したタフラブはデタッチメント(脱愛着)をうたっている。それが「手放す愛」なのだ。(p30)
タフラブは、相手にわかってもらおう、相手にわからせようとすることのない愛といえる。また、わかってあげようとはしない愛でもある。
(中略)
タフラブは、「理解し合いたい」「コミュニケーションをとりたい」という、時には身勝手な欲望や思い込みを手放す愛でもある。(p120)
千歳に支配されるみなみの姿が痛ましく、同時に歯がゆくもあった由仁も、由仁に「つらければ離れたっていいのよ」と言葉をかけた上司の赤井川(第10話)も、そして「背負いすぎの民やめる!!」と決意しみなみと距離を置いた由仁も(第11話)、薄情ではない。みなみを突き放したわけでもない。また、言うまでもないことだが、千歳を拒めないみなみは悪くない。
彼女たちは、意図せずタフラブに取り組んだのではないか。友人のうずらにどう関わってゆくべきかを相談する際の距離感も(第14話)、由仁がトライする「本当のおせっかい」も(第16話)、自分たちの関係性の輪郭や境界線をそっとなぞり直すような慎重さがある。まさにタフラブの精神だ。
そう思うことは、私に希望をもたらす。
これを読んでいるあなたも、よかったら思い出してみてほしい。みなみと由仁のように、親しかったはずの女友達に連絡をとらなくなったことはないだろうか。とても好きだったのに、直接ケンカらしいケンカをしたわけでもないのに、なんとなく疎遠になったことはないだろうか。
卒業後。就職後。収入が増えた後、あるいは減った後。恋人やパートナーができた後。結婚後、離婚後。出産後。あるタイミングから、以前のように楽しく喋れなくなったことはないだろうか。
たとえば、映画『子猫をお願い』(2001年、韓国)では、高校生活を仲睦まじく過ごした女性五人が、卒業後、世間に蔓延るルッキズムや経済格差や性差別に傷つけられて卑屈になったり、互いに嫉妬心を抱えたりする過程が繊細に描かれている。このあらすじ、身に覚えはないだろうか。
個人個人の相性の良し悪し以前に、あらゆる場所、あらゆる人間関係にアメーバのごとく侵入する男性中心的・家父長制的価値観によって女性と女性のつながりが切り刻まれたことや、対立を煽られたことはないだろうか。私にはある。
かつて「思ったことは吐き出したいけど知らん人にジャッジされたくない」(第1話)と居酒屋のトイレから第四の壁を破って主張していたみなみは、由仁の「気持ちをちゃんと言葉にするところ」が好きで、10年かけて自身も「「言葉」を手に入れた」と語る(第11話)。こんなふうに、女友達はもっと豊かに、もっと勇気と安寧をもたらす関係になれるはずなのだ。みなみと由仁のような友情の再構築が、あなたと誰かにも、私と誰かにも、もしかしたら可能かもしれない。