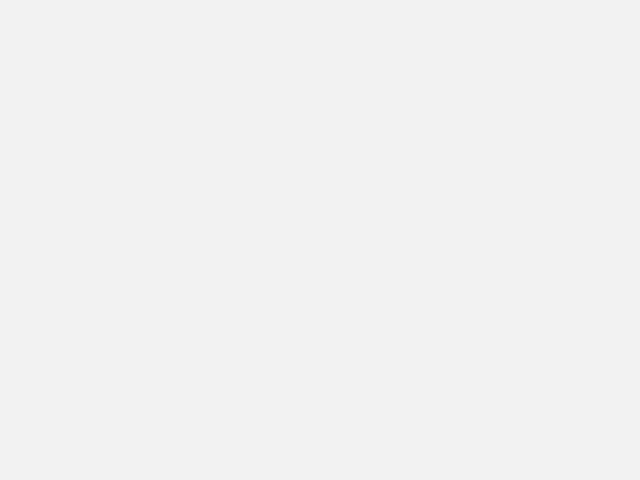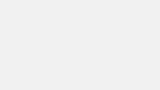東京生まれ東京育ち、裕福な開業医の親と松濤で暮らす27歳の榛原華子(門脇麦)は、結婚を考えていた恋人にフラれてしまう。その後の縁談や紹介などはどれもうまくいかない。結婚こそ幸福だと教育され、それを信じてきた華子は焦るが、義兄の友人・青木幸一郎(高良健吾)に出会って恋に落ちる。
交際は順調に進み、半年ほどでプロポーズされる。しかしその晩、幸一郎の携帯が、時岡美紀(水原希子)という人物からのメッセージを受信したことに華子は気づく。美紀は幸一郎の同級生で、富山から上京して慶應義塾大学に入学したものの、実家の金銭的な事情で学費を払い続けることができず、中退した女性だった。
2021年 日本
監督 岨手由貴子
人が違えば、当然ながら送ってきた人生が違う。見たものが、見なかったものが違う。経験が違う。
『あのこは貴族』は、東京で暮らす二十代後半の女性ふたりを対比しながら、両者の相違点をこまやかに浮かび上がらせてゆく。華子がバーキンをさらりと持つ一方、美紀はエルエルビーンのトートバッグを愛用する。美紀がホテルのラウンジでカトラリーを落とすと、華子は最小限のしぐさで店側に合図を送る。あまり好きではないデザインのマグカップを、「ダサいんだけどさ、手に馴染んで飲みやすいんだよね。全然気に入ってないんだけど、なぜか割れずに生き残っていくし」という理由で使い続ける経験が、美紀にはあって華子にはない。
彼女たちの装いや身のこなしや物事に対する反応のひとつひとつに、これまで送ってきた人生と、培ってきた経済感覚の違いが滲む。どんな言葉よりも雄弁に。
華子の友人・逸子(石橋静河)の引き合わせによって、華子と美紀は出会う。双方が複雑な視線を向け合うが、ふたりの仲を絶対に険悪にしないのが、この映画のもっとも大切なところだ。その思いは、浮気者の父親と、金銭的な事情や体面を気にして離婚を選ばない母親を持つ逸子のセリフにも込められている。
「日本って、女を分断する価値観が普通にまかり通ってるじゃないですか。おばさんや独身女性を笑ったり、ママ友怖いって煽ったり、女同士で対立するように仕向けられるでしょう? 私、そういうの嫌なんです。本当は女同士で叩き合ったり、自尊心をすり減らす必要ないじゃないですか」
本作を観ていると、しみじみと思い知る。「東京に住む二十代の女性」という共通点だけで華子と美紀をひとつのカテゴリーに括ることが、いかに乱暴であるかを。性別が同じでも、年代が同じでも、暮らす都市が同じでも、違って当然のことが星の数ほどあることを。《華子&美紀》よりは近い経済環境下で育ったであろう《華子&逸子》でさえ、結婚や職業に対する価値観は一致しない。
女性と女性のあいだに共通性を見出す喜びや、それによって得られる心強さはたしかにある。一方で、女性全体を安易に「同じ集団」として捉えることは多くの危険をはらむ。女性は──すべての性は──ひとりひとり異なる人生を送っている。首都圏出身と地方出身の差、実家の経済状況の差、教育を受ける機会の差、雇用形態の差……挙げればキリがないだろう。
しかし、ひとりひとりの人生は違いつつも、それらは孤島と孤島のように遠く海を隔てているわけではない。そう信じたい。ある女性の苦悩の一部は、別の女性の苦悩や、あるいはかつて苦悩しながら乗り越えてきたことの一部にそっと重なったり、繋がったり、交差したりしている。その交差点で女性たちは手を振り合ったり、励まし合ったり、救ったり救われたりすることができる。そういう瞬間を、希望と呼びたくなるのである。
プランターと土を用意して、「何か育ててみようかなって。やったことないけど。トマトとか、今の時期に植えるといいみたいだし」と語る華子は対照的に、美紀が暮らす部屋には、すでに至るところに植物が置いてある。狭いながらもすべて美紀の選択によって集められた品で満ちた生活空間の描写や、起業の話題などを織り交ぜながら、美紀が華子とはまったく別の経験値を豊かに積み重ねていることを窺わせる。
華子との対比で「持たざる者」として描かれがちな美紀だが、彼女の人生へのライトの当て方がとても優しい。両者間に大きな経済的格差はあれど、美紀が裕福な華子に嫉妬したり恨んだり嫌ったりするような単純な話の運びにはならない。本作は、徹底して美紀と華子を対立させない。炙り出されるのは社会構造のいびつさだ。
「うちの地元だって、街から出ないと親の人生トレースしてる人ばっかりだよ」という美紀のセリフは、華子にも幸一郎にも刺さる。「街」というのは、単に居住区だけを指すのではない。東京生まれ東京育ちでありつつ、美紀の家のベランダから見えた東京タワーがひどく新鮮だったように、同じ東京で、違う生き方をすることはできる。
そういう可能性の幅を華子に提示したのが他ならぬ美紀であることと、悔しい思いを山ほどしながらも美紀が新しい仕事を懸命に切り拓いていることに、大きな喜びを感じるのである。