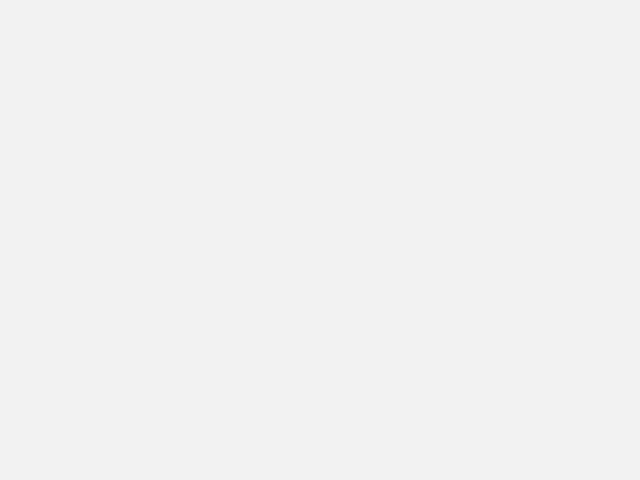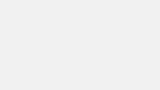スチュアート(エミリオ・エステベス)は、オハイオ州シンシナティ公共図書館に勤める図書館員だ。同館では、近隣のホームレスたちが開館と同時に訪れ、トイレで身支度を整えたり暖をとったりして一日を過ごすのが日常になっている。
ある日、スチュアートと警備員のラミレス(ジェイコブ・バスガス)が、体臭のきつさを理由にアイクというホームレスを退館させたことが問題になる。職員や他の利用者から苦情がきたゆえの対応だったが、体臭を理由に特定の利用者を追放するのは権利の侵害であり、差別であるというのだ。
そんな折、記録的な大寒波が到来する。市が設置したホームレスのためのシェルターは数が足りない。凍死を逃れるべく、大勢のホームレスが図書館を緊急シェルターとして頼ろうとするが……
パブリック 図書館の奇跡(The Public)
2018年 アメリカ
エミリオ・エステベス
現在は仕事を持ち、清潔な家で慎ましく暮らしているスチュアートだが、アルコール依存症に苦しんで路上生活を送った過去がある。
彼はそのことを、図書館に共に立てこもるホームレスたちに積極的に語らない。同じ経験があるからあなたたちの辛さがわかるよ、というアプローチを選ばない。スチュアートは「かつて同じ経験をした者として」ホームレスたちを大寒波から守るのではなく、公共施設の職員として、ひいては社会の一員として守るのである。
ある問題に対し、「同じ経験があるから」とか「自分や家族に起こったこととして想像したら辛いから」といった動機で関わるのが、つねに正解であるとは限らない。たとえば、痴漢や性加害について、「自分の子や配偶者が被害に遭う場面を想像するととても辛い。だから防止を訴える」というアプローチは、一見正しいようでそうではない。被害者が自分にとって身近な人間だろうが赤の他人だろうが、人権は等しく守られるべきなのだから。
かつてホームレスだったスチュアートは、その当事者性を前面に押し出して警察や世論に訴えることはない。ホームレスだったからこそ知っていることは、もちろんたくさんあるだろう。路上の冷たさや、そこで眠る厳しさと心細さ。けれど、「当事者だったから」、あるいは「当事者の気持ちを想像したら辛いから」だけでは、この映画の主題に沿わないのだ。報道番組のインタビュアーに図書館内の現状を説明する際、「ごく身近な人道的危機」と返したスチュアートの言葉のチョイスは、まったくもって的確なのである。
しかし、図書館内に立てこもるホームレスたちのなかに、女性のホームレスが(おそらくはひとりも)いないことが気になった。冒頭、アシーナという女性のホームレスが登場したが、スチュアートやラミレスとの会話内容から察するに、彼女もほとんど毎日のように図書館を利用していたはずだ。アシーナは大寒波の夜をどうやって乗り越えたのだろう?
さまざまな立場や経歴のキャラクターたちを複雑に交差させ、公共という場所とその役割を問いかける堅実な脚本であっただけに、「女性のホームレス」像がすっぽりと抜け落ちていたことは残念でならない。